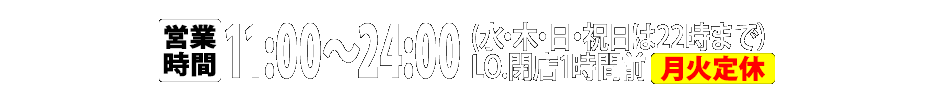お彼岸といえば「おはぎ」をお供えするが、なぜおはぎをお供えするのかというお話。まずお彼岸とはなにかを解説していこう。
日本古来の習慣として根付いているお彼岸の語源は仏教からきている。煩悩に満ちた現世を「此岸しがん」、悟りの境地であるあの世を「彼岸」と呼び、此岸と彼岸の間には三途の川が流れている。
仏教においてお彼岸は此岸と彼岸が最もと近くなる期間とされていて、お彼岸にご先祖様を供養することで極楽浄土へ近づけると信じられていた。お彼岸にお墓参りをするのはその風習からだという。
さて、おはぎをお供えする理由だが、あんこの材料「小豆」には、魔除けや不老長寿の願いが込められているからだという。中国では、赤色には邪気を払う力があるとされ、日本でも赤色には特別な力があると考えられてきた。そのため小豆は赤色なので縁起が良い食べ物とされ、お彼岸にあんこを使ったおはぎがお供えされるようになったのだ。
つぎに「おはぎ」と「ぼたもち」の違いだが、春のお彼岸は「ぼたもち」秋のお彼岸は「おはぎ」というのが正解なのだという。地域によっては作り方や材料に違いはあれど、現在はおはぎもぼたもちも同じという認識で良いのかもしれない。
ぼたもちは、春の花「牡丹」にちなんでおり、おはぎは秋の七草「萩」の花にちなんで名付けられている。お彼岸の季節に美しく咲く花に準えたものをお供えすることで、ご先祖様を供養するという風習だ。
春のお彼岸3月17日から23日まで。春分の日を中日として前後3日間。春本番の暖かな日に、ご先祖様を敬い供養する気持ちがこめられたおはぎを持っておでかけするのもいいかもしれない。